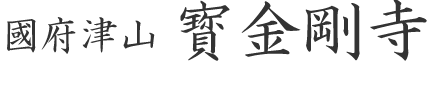四 季
Four Seasons
春
寳金剛寺の四季は梅林から始まります。2月から3月、白梅や紅梅が富士山を背景に咲き誇り、境内は春の香りに包まれます。梅に続き、桜、しゃが、躑躅、藤と百花繚乱、境内が花で覆われる季節です。
Please click photo

紅梅と鐘楼
2月中旬、鐘楼周りの紅梅、白梅が花開きます。お寺の周辺は3月上旬まで梅祭りで賑わいます。
春の山門
2月 山門をお入りいただくと満開の梅がお迎えいたします。
春告げる蕗の薹
2月 早咲きの梅が散り始めるころ、足元ではふきのとうが顔を出し春の訪れを告げています。
零れ(こぼれ)梅
2月 この日は二十四節気の雨水。水ぬるむ季節、春らしい風景が境内のあちこちで見られるようになります。
梅満開
3月 お寺は梅の花と香りに包まれます。蜜を求めてメジロが忙しそうに飛びまわります。
枝垂れ桜
4月 庫裡前の枝垂れ桜も花開き境内は春本番です。
著莪(シャガ)
4月 桜が終わると木陰の著莪(シャガ)が一斉に咲きはじめました。夕方には萎んでしまう一日限りのお花です。
つつじ
4月下旬 境内のあちこちで色とりどりのツツジが咲き始めます。
あやめ
気品のある青、まっすぐに伸びた緑、5月は境内の色合い変わる季節です。
庫裡の藤棚
5月 庫裡の山藤が満開となり、藤棚にはうっすら甘い香りが漂います。
青もみじ
5月 清々しい新緑の季節、青モミジが小さな赤い実をつけました。
梅花空木
5月 俯き加減に咲く梅花空木(バイカウツギ)、一輪挿しに良く似合うお花です。

鐘楼周りの紅梅
2月中旬、鐘楼周りの紅梅、白梅が花開きます。お寺の周辺は3月上旬まで梅祭りで賑わいます。
春の山門
2月 山門をお入りいただくと満開の梅がお迎えいたします。
春告げる蕗の薹
2月 早咲きの梅が散り始めるころ、足元ではふきのとうが顔を出し春の訪れを告げています。
零れ(こぼれ)梅
2月 この日は二十四節気の雨水。水ぬるむ季節、春らしい風景が境内のあちこちで見られるようになります。
梅満開
3月 お寺は梅の花と香りに包まれます。蜜を求めてメジロが忙しそうに飛びまわります。
枝垂れ桜
4月 庫裡前の枝垂れ桜も花開き境内は春本番です。
著莪(シャガ)
4月 桜が終わると木陰の著莪(シャガ)が一斉に咲きはじめました。夕方には萎んでしまう一日限りのお花です。
つつじ
4月下旬 境内のあちこちで色とりどりのツツジが咲き始めます。
あやめ
気品のある青、まっすぐに伸びた緑、5月は境内の色合い変わる季節です。
庫裡の藤棚
5月 庫裡の山藤が満開となり、藤棚にはうっすら甘い香りが漂います。
青もみじ
5月 清々しい新緑の季節、青モミジが小さな赤い実をつけました。
梅花空木
5月 俯き加減に咲く梅花空木(バイカウツギ)、一輪挿しに良く似合うお花です。
夏
境内は、春のお花のあと紫陽花までしばらく花の端境期に入りますが、木々の緑は日一日ごとに色濃くなっていきます。6月、境内の梅がビッシリと実を付け収穫が始まります。
梅雨時、参道沿いで紫陽花やクチナシが花開き、梅雨明けとともに蓮、百合や百日紅など盛夏の花に引き継がれて行きます。
Please click photo

くちなし
6月 梅雨時、境内に甘い香りが漂います。クチナシは仏典に出てくる薫り高い花の瞻蔔(せんぷく)に似ているとされ寺院によく植えられるようになりました。
梅の収穫
6月 ひと雨毎に梅の実がどんどん大きくなります。梅雨の晴れ間にいよいよ収穫です。
完熟落ち梅
6月 参道脇の完熟落ち梅。この時期、参道は梅の香いっぱいの片側通行です。
山門脇の紫陽花
6月 山門脇の白アジサイ。咲きはじめはうっすら緑色ですが、次第に白に変わります。
梅雨明け近し金糸梅
6月 梅雨が終わりに近づくと金糸梅(キンシバイ)が鮮やかな黄色の花を開きます。
仏法花の木槿
7月 洋風に見える木槿(ムクゲ)ですが仏教では仏法を象徴するお花と言われ、奈良時代の栽培記録が残る歴史あるお花です。
盆花の禊萩
7月 梅雨明けのころ禊萩(ミソハギ)が咲き始めます。別名、盆花や精霊花といわれるようにお盆には欠かせないお花です。
本堂前の蓮鉢の蓮
7月 本堂前の蓮鉢の蓮。境内でひときわ存在感を放ちます。
蓮の香
7月 蓮の淡い香りは何に例えれば良いのでしょうか。早朝、無風の時だけの楽しみです。
鉄砲百合
8月 参道脇のあちこちでてっぽう百合が花開きます。夏の青空が似合うお花です。
百日紅の老木
8月 山門前の百日紅の老木が、猛暑に負けず優しいお花を咲かせます。
ダイヤモンド富士
4月と8月のダイヤモンド富士。お寺から年に2回だけ見ることができる一瞬の光景です。

くちなし
6月 梅雨時、境内に甘い香りが漂います。クチナシは仏典に出てくる薫り高い花の瞻蔔(せんぷく)に似ているとされ寺院によく植えられるようになりました。
梅の収穫
6月 ひと雨毎に梅の実がどんどん大きくなります。梅雨の晴れ間にいよいよ収穫です。
完熟落ち梅
6月 参道脇の完熟落ち梅。この時期、参道は梅の香いっぱいの片側通行です。
山門脇の紫陽花
6月 山門脇の白アジサイ。咲きはじめはうっすら緑色ですが、次第に白に変わります。
梅雨明け近し金糸梅
6月 梅雨が終わりに近づくと金糸梅(キンシバイ)が鮮やかな黄色の花を開きます。
仏法花の木槿
7月 洋風に見える木槿(ムクゲ)ですが仏教では仏法を象徴するお花と言われ、奈良時代の栽培記録が残る歴史あるお花です。
盆花の禊萩
7月 梅雨明けのころ禊萩(ミソハギ)が咲き始めます。別名、盆花や精霊花といわれるようにお盆には欠かせないお花です。
本堂前の蓮鉢の蓮
7月 本堂前の蓮鉢の蓮。境内でひときわ存在感を放ちます。
蓮の香
7月 蓮の淡い香りは何に例えれば良いのでしょうか。早朝、無風の時だけの楽しみです。
鉄砲百合
8月 参道脇のあちこちでてっぽう百合が花開きます。夏の青空が似合うお花です。
百日紅の老木
8月 山門前の百日紅の老木が、猛暑に負けず優しいお花を咲かせます。
ダイヤモンド富士
4月と8月のダイヤモンド富士。お寺から年に2回だけ見ることができる一瞬の光景です。
秋
法師蝉が鳴き始めるころ本堂前の赤萩に続き、山門の白萩が参道を覆い尽くすように咲きこぼれます。
秋雨が降り続くと梅林では彼岸花が一斉に咲きはじめます。金木犀の大樹が黄橙色の花をつけ香りが境内一円に広がるのもこのころです。
小田原地方は温暖な気候のため紅葉は遅く11月下旬から12月にかけて境内はゆっくりと秋色に染まります。
Please click photo

本堂前の赤萩
9月 本堂前の萩の花が参道を覆うように咲きはじめます。
山門脇の白萩
9月 本堂の赤萩に少し遅れて山門脇の白萩が満開となります。
一斉に彼岸花
9月 秋雨が降ると梅林では彼岸花が一斉に咲きはじめます。
モチの実
10月 ちょうど当山お施餓鬼のころです。庫裡玄関前のモチの実が赤く色づきます。
本堂中庭
11月 本堂中庭のモミジが少しづつ色づき始めます。黄緑から黄、橙へと四季の移ろいが一番感じられる時期です。
秋のつくばい
11月 ひっそりと置かれた蹲ですが、このころは存在感を放ちます。
大楓
11月 つくばいに紅葉を散らすのはこの大楓です。
銀杏黄葉
11月 境内中央の銀杏が色づきます。本堂前は黄色の落ち葉で覆われます。
縁起木
11月 縁起物のセンリョウ。秋も深まり、いかにも福を招いてくれそうな色合いになりました。
いろはもみじ
12月上旬 お寺で一番鮮やかなモミジです。この年は特に綺麗な赤色になりました。
山門の紅葉
12月上旬 秋の最後を締めくくるのが山門脇のこのモミジです。
雨の散り紅葉
12月中旬 冷たい雨の散り紅葉はひときわ綺麗です。

本堂前の赤萩
9月 本堂前の萩の花が参道を覆うように咲きはじめます。
山門脇の白萩
9月 本堂の赤萩に少し遅れて山門脇の白萩が満開となります。
一斉に彼岸花
9月 秋雨が降ると梅林では彼岸花が一斉に咲きはじめます。
モチの実
10月 ちょうど当山お施餓鬼のころです。庫裡玄関前のモチの実が赤く色づきます。
本堂中庭
11月 本堂中庭のモミジが少しづつ色づき始めます。黄緑から黄、橙へと四季の移ろいが一番感じられる時期です。
秋のつくばい
11月 ひっそりと置かれた蹲ですが、このころは存在感を放ちます。
大楓
11月 つくばいに紅葉を散らすのはこの大楓です。
銀杏黄葉
11月 境内中央の銀杏が色づきます。本堂前は黄色の落ち葉で覆われます。
縁起木
11月 縁起物のセンリョウ。秋も深まり、いかにも福を招いてくれそうな色合いになりました。
いろはもみじ
12月上旬 お寺で一番鮮やかなモミジです。この年は特に綺麗な赤色になりました。
山門の紅葉
12月上旬 秋の最後を締めくくるのが山門脇のこのモミジです。
雨の散り紅葉
12月中旬 冷たい雨の散り紅葉はひときわ綺麗です。
冬
12月、参道沿いの水仙が咲きはじめます。花期は長く春まで咲きつづけ、冬の境内の数少ない色合いとなってくれます。
新年に入ると蝋梅が黄色い花を咲かせ甘い香りが山門周りに漂います。
梅のつぼみもゆっくり膨らみはじめ、寒椿は赤い花をつけ春の訪れを待ちます。
Please click photo

冬紅葉と水仙
この年は12月まで色鮮やかな紅葉が残り水仙と重なる風景となりました。
蝋梅の香り
1月 山門をくぐると甘い香りが漂ってきます。蝋梅は新年最初のお花です。
シダの紅葉
1月 木々の葉が落ちた真冬、足元ではシダが紅葉していました。こんなにきれいに色づくのは久しぶりこれはです。
八重咲き寒紅梅
1月 きりっとした空気の中、最初に咲く梅が本堂前の八重咲の寒紅梅。濃い紅色が冬の青空によく映えます。
雪の山門
令和8年2月は数年ぶりの積雪となり、山門は幻想的な佇まいとなりました。
ひっそりと侘助
2月 境内にはいろいろな椿が植わっています。これは薄桃色の侘助椿です。雪を被ってひっそりと咲いていました。
蝋梅満開
2月 蝋梅満開、まだ寒い中でも明るい春の兆しを感じさせてくれるありがたいお花です。
落ち椿
2月 落ちてなお鮮やかな赤のヤブツバキです。花がポトリと落ちるので、茶花以外ではあまり好まれていないようですが、仏教では聖木とされています。
庫裡から望む富士
2月 庫裡玄関からは木々の間に富士の雪景色が望めます。

冬紅葉と水仙
この年は12月まで色鮮やかな紅葉が残り水仙と重なる風景となりました。
蝋梅の香り
1月 山門をくぐると甘い香りが漂ってきます。蝋梅は新年最初のお花です。
シダの紅葉
1月 木々の葉が落ちた真冬、足元ではシダが紅葉していました。こんなにきれいに色づくのは久しぶりです。
八重咲き寒紅梅
1月 きりっとした空気の中、最初に咲く梅が本堂前の八重咲の寒紅梅。濃い紅色が冬の青空によく映えます。
雪の山門
令和8年2月は数年ぶりの積雪となり、山門は幻想的な佇まいとなりました。
ひっそりと侘助
境内にはいろいろな椿が植わっています。これは薄桃色の侘助椿です。雪を被ってひっそりと咲いていました。
本堂雪景色
境内は静寂さに包まれたモノクロームの世界となりました。
蝋梅満開
2月 蝋梅満開、まだ寒い中でも明るい春の兆しを感じさせてくれるありがたいお花です。
落ち椿
2月 落ちてなお鮮やかな赤のヤブツバキです。花がポトリと落ちるので、茶花以外ではあまり好まれていないようですが、仏教では聖木とされています。
庫裡から望む富士
2月 庫裡玄関からは木々の間に富士の雪景色が望めます。